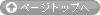電子カルテよもやま話
この頃、気になること
病院の診療支援システムに携わって40年弱となります。
当初はメーカーの立場で仕事をしていましたが、ここ10年ほどは現場での保守運用を支援しています。
始めたばかりですが新旧織り交ぜて好き勝手なことを綴りたいとおもいます。
2021.12.22 処方オーダーの導入効果
私が処方オーダーに関わったのが1998年頃でしょうか。患者サービスの向上が目的に導入されるています。
当時、オーダリングは、処方、診療予約、検体検査がシステム化を行うことが多かったと思います。
システム化については導入費用が高価であったことで費用対効果が優れている業務をメインに進められました。
処方オーダーですが
その頃は、医薬分業は浸透しておらず、院内で処方し患者が持って帰るスタイルが一般的で、
患者は、診察で待たされて、さらに薬の調剤で待たされることがあたりまえでした。
患者さんに薬が手渡されるまでの流れを簡単に説明すると
a) 医師が診察室で処方箋を作成
b) 会計票、カルテと一緒に処方箋を計算窓口へ提出
c) 計算窓口から処方箋を院内薬局へ渡し、調剤が開始
d) 会計で清算し、領収書と薬引換券をもらう
e) 調剤を待って薬を薬引換券と交換し帰宅
医療施設によって若干の流れは変わりますが、概ねこんな感じでした。
これが処方をオーダリングシステム化を行うと
a) 医師が診察室で処方を入力する
に変わります。
実はこれが絶大な効果を発揮します。
医師の処方内容は、院内薬局に出力され、会計計算まで待たずに調剤を開始できます。
さらに処方内容は会計に連動し入力計算の手間を省きます。
これで薬の調剤待ちがずいぶんと改善されました。
当時、院内薬局の前は薬待ちの患者でいっぱいでしたが、効果は目に見えていました。
2021.11.11 前回の処方を変更して処方箋を発行した?
・薬を出すなら新規で処方をお願いします
タイトルでピンとくる方は問題ありません。
この問題、院外薬局から疑義照会でわかることが多いのですが、処方箋の発行日が過去になっています。
処方箋の有効期間は、発行日を含めて4日なので、薬局は調剤して患者にお薬を渡すことができません。
処方の機能(処方に限ったはなしではないですが)は、大きく新規/変更/参照となります。
細かく言うと、前回処方とかDo処方で新規に処方を出す機能もあるかと思いますが、基本は変わりません。
前回処方とか過去の処方を参照してて、間違ってそのまま変更して処方箋を出したりすると、調剤薬局から電話がかかってきます。
だいたい、電話の先は院内の薬剤科となるケースが多いかと思います。
そして、医師の異動が多い時期に頻発します。
電子カルテ操作に不慣れなことが一番の原因かと思いますが、なくなることはありません。
いろいろ考えます。
過去の処方を変更したら警告メッセージを表示するとか、「ほんとに良いのですか」的なメッセージを入れるのです。
しかし、効果は薄かった。評判もよくない。
医師は、処方だけでなくカルテ記載やら他のオーダー発行等で忙しいので、メッセージなんかエンターキー一発で読み飛ばしです。
そもそも、余計なメッセージなんて出すな、ワンクリックでも増やすな。と怒られます。
結論、これは出来ないようにするしかない。
しかし、間違いを訂正する機能が失われることは許されません。
そこで外来診察のPCで院内処方箋に限り処方箋の発行日から4日過ぎたら変更不可としました。
これはわりと効果があったようです。
現在、電子カルテはシェアの高いメーカーに変わり、処方箋の発行日から4日過ぎたら変更不可の機能はありません。
操作の不慣れが要因とすれば、メーカーによる操作性の違いがないことが一番かなと思ったりします。
2021.11.5 病名の管理
・病名は医師が付ける
・病名はカルテに記載する
頭ではわかっていても、できていない病院は多いのではと思います。
近年、電子カルテ等の診療支援システムがサポートされ、病名オーダー等で病名を管理している病院も多くなってきました。
電子カルテで登録された患者病名は、医事システムに連動され、レセプト等の請求にも使用されます。
医事課の病名登録の手間が減るわけです。
しかし、請求事務の都合で病名を追加したり削除したりする場合があります。
例えば、胃にきつい薬を処方するときに胃薬をあわせて処方しますが、胃炎とか追加するような感じです。
ここで、医事側の患者病名を操作すると、医事会計システムと電子カルテの患者病名に乖離が生じてきます。
医事会計システムの患者病名のみ変えてしまうからです。
結果、医事側には電子カルテにない病名が増え、同じ病名でも開始日が医事と電子カルテで異なってきたりと、収拾がつかなくなります。
患者病名は重要な診療情報であり、統計的にも重要なポジションを占めます。
医事側には電子カルテも信用できない患者病名では、なんとも情けない状況となります。
電子化した意義もありません。不正確な情報は価値がないからです。
重要なのは、病名に関する運用を取り決め、順守することです。
・病名は、医師が診断し登録
・医事の請求事務上で追加変更が必要な場合は、医師に連絡し対応
・医師補助による代行入力と医師の承認
ただし、外来診療で病名がつけられた場合、その患者が来院しなければ、ずっと転帰もせずに残ります。
ちなみに私が病名オーダーの導入をコンサルした病院では
・病名は医師が登録
・医師への依頼は連絡票で
・レセプト時期は、レセプトに赤書き、医師にレセプトチェックを回して対応
・外来で、開始から1か月以上経過したら自動で転帰するチェックをサポート
としました。
20年弱前ですので、カルテは紙でした。
病名オーダーで更新された情報は、シールプリンタに印刷しカルテに張り付けサポートまで行っています。
取り纏め担当の医師は、支払基金で審査も担当されたこともあり、すぐに理解頂けたことが幸いでした。
2021.11.2 病名管理(前置き)
懸案の一つに病名の管理があります。
管理の話の前に病名に関連した統計について少々・・・
例ですが、「ある期間にA病名の外来受診患者数」といった漠然とした値を求められることがよくあります。
せめて延べ患者数とか実患者数とか教えてほしいのですが、大概が院外からの問い合わせなので誰も答えられないことがままあります。
なので、漠然とした要求には意味をつけた値を回答するようにしています。
意味をつけて回答しても所詮は自己満足です。
問題は、何をもってカウントを取るか、そしてカウントは正しく求められるのかです。
a) その期間のレセプトからA病名を拾い上げ延べ患者数として計上
→みんなが月1回の通院とは限らず、意味付けが難しい値です。
→患者数を延べ数とするなら、レセプトの診療実日数を意識すれば良いような気がします。
しかし、A病名外で受診することもあるので過剰な概算値となります。
→結局レセプトに頼らず、A病名の付いている期間に該当診療科の受診日数をカウントすることになります。
b) 延べではなく実患者数を求めた場合
→ a)で求めたデータから患者で病名をまとめれば実患者数がわかります。
しかし、気をまわしすぎて、転帰し再発した場合のカウントアップは必要ないのかと少し考えてしまいます。
c) A病名の診断がなされた件数を求めたい場合
要は、A病名の発生件数です。
→A病名の開始と転帰を意識しなければ正しい数は出ません。
開始の数をカウントすれば求める数となるような気がします。
が、レセプトの開始日を信じてよいかのな悩みます。
請求上の理由で治療中と思われるのに初診開始とするケースがあるからです。
ぐだぐだですが、結論は病名がきちんと管理運用されていれば悩むこともないのにと思います。
2021.10.18 診断結果の既読チェック
患者の担当医師が病理診断、画像診断の報告書(レポート)を未読のまま放置し、結果、治療が遅れ、患者に不利益をもたらした。
近年、このような報道も多くなり、厚労省からも対策の通達が出されています。
事情はあるのでしょうが、検査料を取っておいて結果を放置し手遅れとは、全くよろしくない話です。
令和元年の12月、厚労省から「画像診断報告書等の確認不足に対する医療安全対策の取組について」が通達されました。
要は、組織的な伝達体制や確認体制を構築が望ましいとのことです。
それまでにも注意喚起レベルの通達はありましたが、対策まで言及しています。
医療機関、学会は、具体的な対応方法を検討するわけですが、規模、資金により次の観点での検討が必要になります。
・運用での対応
・導入済みツールを流用し対応(ToDo、Work Flow、owMail等々)
・電子カルテ等のシステム的な対応
これらについては多くの事例がweb上にあるのでここでの説明は省きます。
私が関係する病院は、画像検査は電子カルテで、病理は部門で未読チェックをサポートしています。
最近、医師からこんな発言がありました。
「電子カルテで(画像検査の)未読チェックはサポートされているが、自分の出したオーダについてのチェックです。
指導医は研修医の出したオーダの未読までチェックできるようになりませんか。」
なるほど、さもありなん。
既に他病院では要望が出され、個別に対応されているようです。しばしのお待ちを・・・